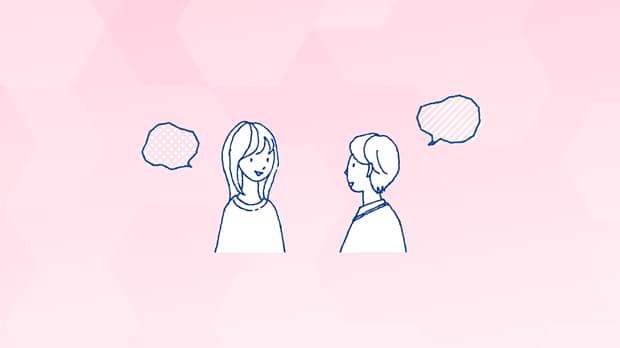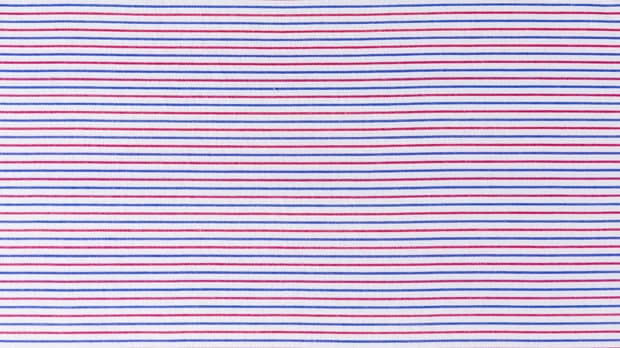あけましておめでとうございます。今年も皆様の健康づくりや食生活に役立てていけるような情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
年末年始は忘年会や新年会、おせち料理などたくさん楽しまれた方が多いと思います。年末年始に食べる料理には胃腸に負担がかかりやすいものが多く、例えば、おせち料理は日持ちするように糖分や塩分が多く含まれています。また、食べ過ぎなどでも胃腸に負担がかかってしまいます。お正月明けは胃腸に優しいお食事がおすすめです。
1月7日には〝七草がゆを食べてお腹の調子を整える〟そんな風習があります。
今回は「春の七草」について紹介します。
春の七草
1月7日は、「人日(じんじつ)の節句」といいます。古代中国では、この日に七種の菜の煮物や汁物を食べて無病息災を願っていました。一方日本では、お正月に野原の若菜を摘んで食べる「若菜摘み」という習慣があり、七種の穀物で作ったおかゆを食べて五穀豊穣を願う行事がありました。中国の人日の節句の風習と日本のおお正月の風習が合わさって、1月7日の節句に七草がゆを食べるようになったと言われています。
春の七草の植物
- せり
ビタミン、カロテン、鉄分、カリウム、葉酸などが豊富で、食欲増進や整腸作用の働き、貧血の予防や生活習慣病に効果があります。 - なずな
ビタミン、食物繊維、カルシウムなどが豊富で、腸から吸収したカルシウムが骨に沈着するのを助けます。高血圧の予防、解熱等にも使われていました。 - ごぎょう
たんぱく質、ミネラルなどが豊富で、咳止めや痰、喉の痛みを和らげます。風邪予防、むくみ軽減の働きがあります。 - はこべら
たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどが豊富で、利尿や整腸作用があります。歯茎の薬や止血等にも使われていました。 - ほとけのざ
食物繊維、ビタミンが豊富であり、高血圧の予防や整腸作用の働きがあります。 - すずな
ビタミン、カリウムなどが豊富で、整腸作用やむくみ軽減の働きがあります。 - すずしろ
葉にはビタミン、鉄分、カルシウムなどが豊富で、風邪予防や美肌効果があります。根には食物繊維が豊富で、整腸作用の働きがあります。